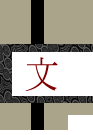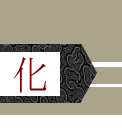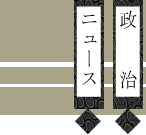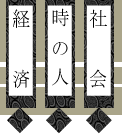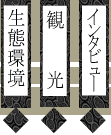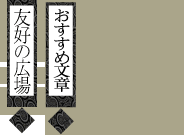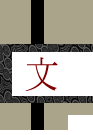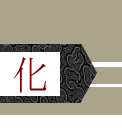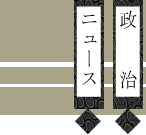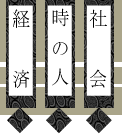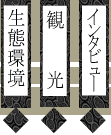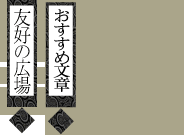|
創造社は、文学研究会に続いて1921年に成立した新文学団体である。
創造社のメンバーの思想的傾向はかならずしも一致していたわけではなかったが、文学的にはほぼ同じ傾向があった。即ち「天才」を崇め、「インスピレーション」を重視し、文学的な「完全」と「美」を求め、文学は「内なる要求」を忠実に表現しなければならない、というものであった。
創造社のロマン主義的傾向の、詩歌の面での代表は郭沫若であり、小説散文の方面では郁達夫であった。
郁達夫(1896―949年)は、創造社のメンバーの中でも小説、散文の創作では、量的にも質的にも第1の作家であり、「五・四」新文学運動のなかでも大きな影響を及ぼした作家である。郁達夫は浙江省の富陽に生まれ、幼い時から中国古典詩文にしたしみ、小説や戯曲を読むことも好んだ。1913年に長兄とともに日本に渡り、名古屋の第八高等学校を経て、1918年に東京帝大の経済学部に入ったが、かれの志向は文学にあった。日本留学の期間に、かれは西洋の文学、特に近代ヨーロッパ文学と日本文学を広く読んで、その影響を受けた。10年に近い異国の生活の中で、郁達夫は、その頃の中国人留学生や華僑の例にもれず、さまざまな差別や冷遇、ときには屈辱を受け、愛国の熱情をかきたてられる一方、世のありさまに怒りと憎しみをもつ、憂うつで多感な性格がますます強くなっていた。こうした生活の経験と思想的な状態は、のちの彼の作品に鮮明に反映されている。1921年、郁津夫は日本に留学した郭沫若、成倣吾、田漢、張資平らと創造社を結成し、小説を書きはじめた。1922年に帰国してからは、積極的に創造社の文学活動に加わり、創造社の刊行物の編集にたずさわり、後には安徽、北京、武昌、広州などの大学で教鞭をとったが、あいかわらず多くの力を創作にそそいだ。
郁達夫の最初の小説集『沈淪』は、作者の日本滞在中の生活と思想を描いたもので、郭沫若の『女神』とならんで最初の「創造社叢書」の一冊として出版された。この小説集には『沈淪』『銀灰色の死』『南遷』の三つの短編が収められている。代表的なものは『沈淪』である。この小説は、一人の憂うつ症の中国人留学生が、純真な友情と温かい愛情を渇望しながら、異国で屈辱と冷遇を受け、ついには絶望から沈淪に至る過程を描いたものである。主人公のいやし難い憂うつと苦悶は「五・四」の時期のあの重苦しい圧迫の下で目覚めながらも、現状を改革するすべを知らない青年に共通の心理状態を反映しており、時代の特徴をそなえている。
郁達夫は文学創作を始めたときから、鮮明なロマン主義の特徴をもって文壇に現れた。彼は「文学作品はみな作家の自叙伝である」という見解を賛成した。だが、魯迅が小説の中で用いた、「私」を主人公にして深くその心境に立ち入り人物と事件を描写するリアリズムの手法とは異なり、郁達夫は、しばしば「私」を主人公にしながら、抒情的な筆致で大胆な自己暴露と率直な自己表現をおこなって、「重圧の呻吟の声の中に反抗をよせる」のである。『沈淪』の中の小説『風鈴』『懐郷病患者』『蔦蘿行』及び『還郷記』『還郷後記』『離散の前』などは、いずれも「自叙伝」的な性質を帯びたものである。
郁達夫の作品の主な基調は、感傷的色彩の強いロマン主義ではあったが、現実に対する作者の観察がしだいに深まってくるにしたがって、作品におけるリアリズムの要素もたえず高まっていった。『春風に酔いしれる夜』では、うらぶれて、売文生活をしている、心のからっぽな、卑小な「私」と、苦難のなかで頑強に生きていく、心の純潔な、性格のしっかりしたタバコ工場の女工陳二妹との人間像の対比を通じて、女工の美しい魂と素朴な反抗精神をたたえ、現実のみにくさをあばくとともに、「あわれむべき無名文士」の軟弱さ、無力さを風刺している。『薄奠』は一人の人力車夫に対する挽歌である。この善良で職務に忠実な労働者は自分の車を買うことを夢みて、毎日朝から晩まで働きに働くが、結局は車を買う希望は水の泡と帰し、車夫自身も重圧の下で死んでしまう。車夫に対して同情を寄せながら、どうする力もない「私」は、紙で人力車をつくって、車夫に対する「薄奠(ささやかな手向け)」とするのである。
郁達夫の小説では、性愛が重要な位置を占め、しばしばあからさまに「性的変態心理」が描かれている。このため作品のロマン主義はセンチメンタリズムの外に、ある種のデカダンスの色あいをも帯びたものになっている。短編小説『茫々夜』から中篇小説『迷える羊』に至る作品は、いずれも青年の思春期の性の苦悶と紅燈の巻をさまよう生活を描いたものである。女工の生活を主な内容とした中篇『カの情は弱き女』にさえ、性的変態心理の描写がある。こうした描写は、主人公が世を憤り個性の解放を追求することと関連しているのだが、自然主義的な手法で性愛や肉欲を描写すると、いきおい作品の肯定的な思想内容を弱め、場合によっては損なうことになる。中篇小説『迷える羊』では、ストーリーから見て、作者の意図するところは、弱き女優が悲惨な生活の中でみせる力強い性格を描くことにあったのだが、小説では「迷える羊」にも似た彼女が、性愛を得たときの喜びと性愛を失ったときの悲しみに多くの筆をさいたため、小説の積極的な社会的意義を弱めてしまっている。
小説の外に、郁達夫は数多くの散文を書いたが、いずれも水準の高いものであった。かれの小説の多くは、すぐれた筆調で書かれ、散文に近かった。また、かれの散文は優美な筆致で感情がこもり、「才能があり、情感の豊かなインテリが、動乱の社会の中で苦悶するありさまがよく表現されている」。『寒灰集』の中の『ある文学青年に与える公開状』では、悲憤激越の調子で、青年に対して邪悪な勢力に敢然と立ち向かうように呼びかけている。『断残集』の中の「瑣言猥説」編の20数篇の短文は、時事問題を論じ、政治を風刺して、論理明快で一風変わった趣がある。しかし、かれの特色がよく現われているのはやはり紀行散文である。『履痕処々』は、清婉な筆づかいで、平原と沃野、山と河の景色を描いて、そこに作者の思いが託され、言外の意があらわれ、所々に旧体詩が織り込まれ、奥深い境地を見せている。例えば、『釣台の春の昼』は美しい旅行記で、夜に桐廬を訪れ、朝に富春を発ち、沿道の景色の描写は強く人びとの心を打つ。情景描写に国を憂い、民を憂うる心を託したのが、郁達夫の紀行散文の大きな特徴であり、紀行文学という長い間伝えられてきた文学形式に時代の色あいを添えたものである。
張資平(1895〜1959年)はかつては創造社の主要メンバーであり、多くの小説を書き、また比較的早くから長編小説を手がけた。かれは、郁達夫と同様に、日本の留学生活を書くことから新文学の文壇に入った。しかし張資平は郁達夫とは違って、主観的な抒情的色あいの強いロマン主義的な格調はなく、写実的な手法を多く用いて、客観的に人物や物語を描くことに重きを置いた。だが、「彼の『写』も『実』も表面的な現象にすぎず、事実の核心に触れたことはない」。かれの小説には愛情の悲劇を書いたものが多く、初期の短編『彼女は祖国の天地を悲しく眺める』『梅嶺の春』、長編『沖積期の化石』などの作品では、社会問題をとりあげ、技巧的にもみるべきところがあった。だが後になる程、三角関係の恋愛を書くことに熱中し、はては色魔狂、性欲狂まで登場させ、創造社の戦闘的傾向や「五・四」新文学の反帝・反封建の精神とはますます離れてしまった。
第1次国内革命戦争を経て、創造社には重大な変化が生まれた。郭沫若、成倣吾らの主なメンバーは革命闘争の洗礼を受け、これに新たに日本から帰ってきた青年作家が加わり、創造社を革命的な方向へ旋回させる力となった。1928年、創造社は新たに成立した太陽社とともに、プロレタリア革命文学を提唱し、積極的にマルクス主義の文芸理論の翻訳紹介に勤めた。そうした中で、一部のメンバーは意見が合わなかったり、あるいは政治的な転向のため、創造社から脱退していった。後期の創造社は「左」翼的教条主義の影響を受けて、誤った観点の文章を発表したりもしたが、中国新文学と革命運動の緊密な結びつきを促進するという面では、大きな役割を果たした。
2001年4月10日
|