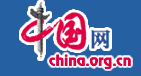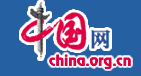かつてアメリカの地理学者ロカは、ナーシー(納西)族の古代王国を研究するため麗江を訪れ、27年もの間、この地に住み続けた。晩年の彼は「玉竜雪山で死にたい」と心の内をもらしていたという。麗江はそれほどに魅力にあふれ、人々の憧れの地であり続けている。
麗江は、雲南省西北部、海抜2416メートルの高原に位置する。ナーシー族の古都として、伝統的住居に代表される民族文化を今につたえ、1997年、ユネスコの世界文化遺産に指定された。
私にとっても麗江は長い間、憧れの場所だった。そしてついにその地を訪れる機会を得て、飛行機の窓から次第に近づいてくる麗江の姿を眺めていると、古都と周囲を取り囲む山々が、丁寧に整えられた箱庭のような美しさで目の前に迫ってきた。標高5596メートルの玉竜雪山は、その名のとおり雪におおわれ、銀の鎧を身につけた武士が古城を守り続けているようだ。やがて麗江に降り立てば、高原の澄み切った空気のなかに、古い家屋、入り組んだ路地が広がり、思い描いていた以上の神秘的な雰囲気に、私はしばし夢見心地になってしまった。
麗江の都が造営されたのは、宋代末から元代初期(13世紀末)にかけてといわれる。当時、漢語では「大研鎮」と呼ばれ、ナーシー族の言葉では、「グゥベン」とか「イクディ」などと呼ばれていた。「イクディ」とは街を流れる金沙江の後背地、というような意味、「グゥベン」は米倉、つまり米の集散地という意味だという。明代初期(14世紀中ごろ)には、麗江は相当な規模の都となり、雲南、四川、チベット一帯の交通の要所だった。清代以降、17世紀中ごろには、麗江は雲南西北部の物資の集散地として、重要な役割を果たすようになっていた。また歴史の一時期、インドからチベット、雲南一帯に向かう隊商たちの通路となっていたこともある。険しい山岳地帯を移動するこうした隊商は馬を連ねたもので、主に茶の取引きをしていた。彼らの移動したルートは「茶馬古道」とも呼ばれるが、麗江は、彼らにとっても重要な街だったのだ。
古都は今も当時の面影をたたえ、車の騒音も、自転車の姿さえもない。私は街で唯一といわれる古い住まいをそのまま使用した旅籠に泊まってみることにした。木造二階建ての上階の部屋をあてがわれたが、階段はのぼりおりするたび、ギシギシと音をたてる。歴史のロマンを感じつつ、窓を開ければ、大通りの東大街が見える。遠くに目をやれば、玉竜雪山。私は沸き上がる興奮にせかされるように、カメラを担いで街にとびだした。
まずは麗江を訪れたほとんどすべての人が行く四方街に向かった。この通りは、東西に約150メートル、道幅は約25メートル。道に沿ってぎっしりと店舗が並ぶため「四方街」と呼ばれる。またナーシー族の言葉では「ジルグ」と呼ばれ、それは「街の中心」という意味だという。元代初期に露天の市場として始まり、清代にはすでに相当の規模になっていたという。当時、市場では土地の布や、穀物、野菜、酒、薪などが売られていた。今もここは街の商いの中心で、店では麗江特産の手作りの銅器、ナーシー族の民族衣装、ナーシー族に伝わるトンバ文字を刻んだ工芸品、高原で採れる希少な漢方薬材、土地の食品などが売られている。だから麗江を訪れた人は、ここを見学し、旅行の記念の品を買うことになる。 四方街は六本の通りとつながっていて、ここから麗江のどこにでも行くことができる。通りには石畳が敷かれており、ところによってそれが縦並びになっていたり、横並びになっていたりする。聞くところでは、往時、不案内な旅人でもインドへ向かう道と、チベットへ向かう道をすぐ見分けることができるように、敷き方が工夫されていたのだという。
明け方、まだ陽がのぼらないうちに散歩をすると、街の人たちは、敷石を水で丁寧に清めている。明け方の光が石の面に映えて、なんともすがすがしく、美しい。朝食をつくる時間になると、人々は家が煤だらけになるのを避けるために、石炭コンロを通りの真ん中に持ち出す。そして煮炊きが始まり、煙が漂う。その数が増えるにつれて、古都の一日はゆっくりとあけていく。ここにはなんと詩情豊かな朝があることだろう。
ナーシー族の女性たちの服装にも私は魅了された。年配の婦人も、うら若い乙女も、みな腰には独特のスカートのような布を巻き、羊皮のショールをはおっている。ショールの背中には「七星」と呼ばれる、丸い模様が七個縫い付けてある。七星は、日、月、星のシンボルで、ナーシー族の女性たちの賢さと勤勉さを象徴するのだという。
ショールの形は、もともとナーシー族の先祖が崇拝していたカエルの形状に由来している。七星はカエルの目でもあるのだという。道端の屋台では、どこででも七星の模様をはめこんだおみやげの類が売られている。
街の西にある獅子山には、木造、五層の楼閣があり「万古楼」と呼ばれる。上層からは麗江の街が遥かに見渡せ、15キロ離れた玉竜雪山も遠くに見える。獅子山のふもとに、かなりの規模の建築群が目に入るが、それは明代以来、この地を支配した土司(土地の少数民族の指導者に皇帝が与えた世襲の官職)の木氏の官邸だ。清代以降、建物は何度も破壊され無残な状態になっていたが、近年、修復された。官邸に入ると、まず石の牌坊(鳥居形の門)が目につく。そこには「聖旨」「忠義」と文字が刻まれた二枚のへん額が上下に掲げられている。明の神宗(1573~1620年)の筆と伝えられるもので、当時の土司と中央政権との密接さを見て取ることができる。ただしこの牌坊の原物は「文化大革命」中に破壊されており、今の建物は近年復元されたものだ。それは確かに一つの代替品にはなっているが、ナーシー族の
歴史の証人である牌坊は、永遠に失われ戻らない。私は悔しく思いながら、さらに建物の見学を続けた。建物は、正殿、光碧殿、玉音殿、三清殿、御園と、一列に奥に連なっており、全体の構造は故宮を思わせる。ナーシー族の文化と中原の文化は、源をたどれば、重なりあう部分が多いのだろう。
夜、辺りは静まり、かすかに楽器の調べが聞こえてくる。人々は三々五々、ナーシー族の古老たちが奏でるナーシー古楽の演奏会場にでかけていく。中国民族音楽の生きた化石、ともいわれるこの音楽は、明清時代、中原から麗江に伝わった道教の音楽がもとになっているという。彼らは中原ではとうの昔に使われなくなった弦楽器や、竹の吹奏楽器、大型の琵琶などを使う。いにしえの調べは、今自分は古代の隊商たちとともに、彼らが旅をした道にいるのではないか、という気分にさせる。
深夜、私は銅鑼の音で目を覚まし、あわてて窓を開けた。それは実は夜番が子の時を人々に告げるものだった。私はいつのまにか身を翻してカメラを抱え、深い眠りのなかにいる麗江の街にまた走りだしていた……。
「人民中国」より 2004年11月4日