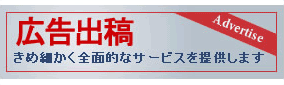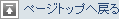「雁陣」のリーダー日本から遠ざかるASEAN
タグ: 中国 経済 日本 雁行型形態 ASEAN
発信時間: 2010-06-21 12:56:03 | チャイナネット | 編集者にメールを送る
中国とミャンマーをつなぐ石油パイプラインの建設は、汎アジア鉄道西部区間建設の足取りを速める。これは中国とASEANの経済貿易協力をさらに推進し、新しい形の互恵的発展を実現することになる。
日本はアジアの雁行形態型経済をリードする「雁陣」のリーダーとされてきたが、中国経済の台頭や中国・ASEAN自由貿易区の構築に伴い、このような雁行形態型経済成長モデルは変化し始めている。
「金融危機が世界を席巻し、アジア地区が産業のモデルチェンジとレベルアップを迫られる中、中国とASEANは既存の協力関係構築における成果を基礎に『雁陣』からの突破という戦略的目標を実現しようとしている」と、暨南大学東南アジア研究所の鞠海竜研究員は話す。
日本をリーダとする「雁陣」への戸惑い
1980年代、日本経済は急成長し、経済学者の赤松要氏は「雁行形態論」を提唱した。この理論に基づくと、当時のアジアにおいて、日本は東アジア地区の産業発展をリードする「雁陣」のリーダーとなる。アジア NIES(韓国、台湾、中国の香港と中国の台湾)がその中心で、ASEANと中国東南沿海地区がその後に続く分業型発展モデルである。
しかし1990年代に入り、数回の金融危機の影響を受け、雁行形態型経済成長モデルの中の主要国や地域の産業発展に新たな動きが現れ始めた。日本をトップとする東アジアの産業分担と産業移転の「雁行形態型モデル」は徐々に崩れていった。
コメント数:0最新コメント
コメントはまだありません。