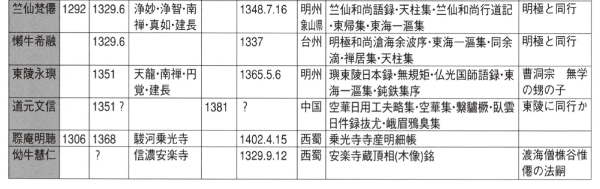| ホーム>>中日両国>>視点 |
| 中日文化交流史の中で僧の果たした役割 |
| 発信時間: 2009-11-19 | チャイナネット |
|
|
|
中世に仏教とともにやってきた文化 新しい宗教はいつの時代でも、ありがたみのある荘厳さの中にも華やかさやある種のきらびやかさがないといけない。空海は華やかな胎蔵・金剛界の両部曼荼羅や、修法や修行に欠かせないこれまでにない新しい密教法具などを日本に持ち帰った。 現代の日本の寺院には黄金に輝く仏像や赤や青の原色を使った建造物はあまり見かけない。おそらく四季のある日本にはそぐわなかったのであろう。中国を旅して思うのは、この原色が大陸の風土にぴったりとして、否応なく存在感をアピールすることである。 中国文化がもろにやってきた奈良時代には「青丹よし奈良の都」と詠われたが、枕詞にもなった「青丹」とは青や赤という意味で、原色の青や赤のきらびやかな建造物が当時の人々を驚かせたことだろう。やがて年月を経て自然の中に溶け込んだ。色あせて風景に溶け込むのをよしとしたのか、日本では塗り替えられることはなかった。 仏教僧が持ち込んできた文化は、当時の日本人にあこがれをもって迎えられた。 『日中を結んだ仏教僧』(農文協『図説中国文化百華』シリーズ)で、頼富本宏教授は、宋代以降の中国仏教、とくに禅宗が日本の衣食住を中心とした日常の生活文化に与えた影響は、唐代仏教をはるかに超える強烈なものであったと述べ、具体例として「普請(ふしん)」「玄関」といった建築用語、「炬燵(こたつ)」「行火(あんか)」などの暖房器具、「豆腐(とうふ)」「味噌(みそ)」「納豆(なっとう)」など今では日本の食卓に欠かせない食品などを例に挙げている。 石川九楊教授はさらに、住生活や調度品の「暖簾(のれん)」「箪笥(たんす)」「椅子(いす)」「算盤(そろばん)」「布団(ふとん)」、食品の「杏子(あんず)」「銀杏(ぎんなん)」「饅頭(まんじゅう)」「麺(めん)」「饂飩(うどん)」「素麺(そうめん)」「蒲鉾(かまぼこ)」「醤油(しょうゆ)」「砂糖」「般若湯(はんにゃとう)(酒)」なども中世に大陸から禅僧が日本に伝えたものとしている。どれも読みをつけなければ、まともに読めそうもない漢字であるが、音読すればはるか昔から日本にあったと思われそうなものばかりである。 今もし、日本から上記の文化やものがなくなったら、日本人はパニックに陥るかも知れない。中には消えつつあるものもあるが、もはや日本人にとっては欠かせない、日本文化にすっかり馴染んだものである。少なくとも小津安二郎の映画には欠かせない、日本的小道具であろう。 また後の時代、江戸時代の初期にやってきた明国の亡命僧・隠元禅師(1592~1673年)が伝えたとされる「隠元豆」、仏事法要などの後にあまねく修行僧に供したとされる精進料理の「普茶料理」も隠元がもたらしたものだという。
茶道と「わび」「さび」  抹茶を点てる。茶道では茶筅で抹茶を点てる。中国から伝わった茶だが、粉茶にして飲む風習は日本の茶道に残る
茶は遣唐使によって平安時代に日本に伝わったといわれる。唐代に仏教寺院で喫茶・食茶の風習があり、日本の「お茶漬け」にあたる「茶飯」を空海や円珍も青龍寺でもてなされたという。 中国では陸羽(733~804年)が『茶経』を著わし、茶の飲み方や歴史について系統だった紹介をしている。日本に伝わった当初は、嗜好品というより薬として飲まれたようである。 この喫茶を文化にまで高めたのは栄西の功績だと頼富教授は前出の著書で述べている。書物として『喫茶養生記』があるが、冒頭に「茶なるものは、末代養生の仙薬なり、茶の飲用は、人倫延齢の妙術なり」と記されているという。 唐代に編纂された禅僧の生活規範集である『百丈清規』に点茶や茶礼などの、茶に関する儀礼が多く記されているとおり、坐禅と喫茶は相補う実用的な関係にあったとされる。 中国でも時代によって茶の飲み方は移り変わったが、宋の時代には粉末にし、湯で溶いて飲む茶、いわゆる抹茶が流行していた、と『火の料理 水の料理』(農文協『図説中国文化百華』シリーズ)の著者で料理研究家の木村春子先生はおっしゃる。この飲み方は中国ではすたれたが日本に伝わって残り、後に千利休(1522~1591年)が「わび」「さび」の境地に高めた茶道となっていく。 自分探しの旅 このように見てくると、日本の文化がいかに中国と深く関わっているかがわかると同時に、仏教と仏教僧が果たした役割の大きさに驚く。日本国中にお寺があり、大都市には間違いなく大寺院が建立され、多くの参拝者が引きも切らず参詣している。全国には寺院の名を冠した地名がどれだけあることだろう。私たちが日常使っている食材、衣服、建物やことばにいたるまで、僧を介して中国とつながっていると考えると、親しみが倍加すると同時に、新たな目でもう一度中国を見てみたいと思わざるを得ない。まるで自分探しの旅に出るように、興味が尽きない。(広岡 純=文 若杉憲司=写真)  「人民中国インターネット版」 2009年11月19日
「人民中国インターネット版」 2009年11月19日
|
|