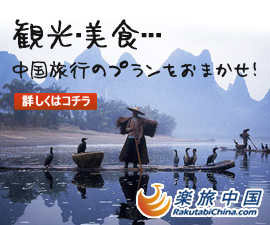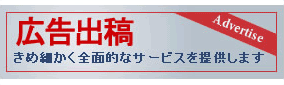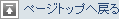オバマ一般教書演説:中国へ4回の言及の良し悪し
オバマ一般教書演説:中国へ4回の言及の良し悪し。 例えば中国への言及は4回あった。これは昨年の2倍で、各国で最も多い。一体これは良い事なのか、それとも悪い事なのか。具体的に検討してみよう…
タグ: 一般 教書演説 オバマ 日本 中国
第2、第3の言及は最初の言及の延長で、米国の潮流や議員の好みに合わせたものだ。中国の発展に米国を含む世界各国が関心や懸念を抱いていることも明らかにしている。特に高速鉄道については、昨年の一般教書演説でも言及があったが、前回は「米国には鉄道においても州間高速道路においても競争力がある。欧州あるいは中国が最速の鉄道を持っているというのは当然ではない」と述べていた。
米議員の関心が最も高かったのは雇用問題に触れた4回目の言及だ。近年、中国人が米国人の雇用機会を奪ったことが中国経済脅威論がもてはやされる理由の1つとなっている。だがオバマ大統領は政府を監督する議員らに対し、中国との合意締結は米国人の雇用機会を増やすと語りかけた。これはもちろん、中国脅威論を解消する効果的な方法の1つだ。
このことからオバマ政権が現在、中国に対して比較的積極的な姿勢であることがわかる。これも先日の胡主席による訪米成功の現われであり、中米関係が昨年来摩擦の絶えなかった難局から徐々に抜け出す見込みのあることを示している。
だが別の角度から見ると、中国への頻繁な言及は中米関係の複雑さを示すものでもある。米国は言及したくない国だけでなく、真の同盟国にも言及する必要はないからだ。例えば英国、イスラエル、日本、韓国などへの言及は少ない。
オバマ大統領は今回、3月にブラジル、チリ、エルサルバドルを訪問し、米州諸国と新たな同盟を築く考えも示した。その結果がどうであれ、米国はこれらの国々を準同盟国と見ており、その密接度も信頼度も「敵でもなく友人でもない」中国を上回っているのである。
ごく短い一般教書演説にも、米国人の他国への評価・親疎が語り尽くされている。中国の国際的地位や影響力の高まりは肯定されたが、イデオロギーの溝は依然埋めがたい。協力「せざるを得ない」情況の下での寒暖は、互いにとうに理解しているはずだ。
「人民網日本語版」2011年1月30日
「中国網日本語版(チャイナネット)」の記事の無断転用を禁じます。問い合わせはzy@china.org.cnまで