
 | 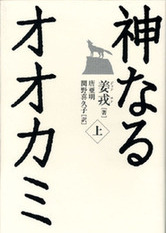 |
『神なるオオカミ』(上・下)日本語版表紙
それを聞いて、ぼくは自分がモンゴル人かウズベキスタンの人に似ていると、何度もロシア人にいわれたことを思い出した。漢民族といっても体や顔つきの特徴からみれば遊牧民族の子孫だと、ある歴史学者から指摘されたこともある。また、中国人の名字のうち、胡、唐、于、斉、姜などは騎馬民族の子孫だという。漢民族とは、じつに様々な地域の人が融合されてきた民族なのである。
姜戎さんの遊牧民としてのオオカミ体験には遠くおよばないが、ぼくもまた違った「農民」としてのオオカミ体験をもっている。1969年、毛沢東の呼びかけに応えた16歳のぼくは、「知識青年」としてシベリアに隣接する黒竜江省の中ソ国境に「下放」された。ソ連との戦争に備え、毎日、軍事訓練をうけながら農作業に従事していた。はてしない三江平原の黒い大地にも、ときどき、オオカミが目の前に現れた。いつも集団で行動していたぼくたち「知識青年」は、オオカミとの間に、ある種の「暗黙の了解」ができていた。オオカミは襲ってこないし、ぼくたちもオオカミを攻撃しない。数十メートル先の丘に立って、こちらをみつめるオオカミの姿は颯爽としていた。空に鼻を突き上げて、「ウォー、オーン」と吠えだす姿もみたことがある。
とはいえ、オオカミの群れはやはり怖いものだった。しかし、オオカミたちは複数の人間には近づいてこない。ある程度の距離をたもちながら、後ろについてうろうろしていた。夜、トラクターで畑を耕していると、野ネズミが出てくる。オオカミの群れはぼくたちのトラクターの後ろで野ネズミを獲っていた。ぼくは鋼鉄の運転室に坐り、ゴーゴーと轟くエンジンの爆音やライトの光に守られていたので、身の危険をそれほど感じなかったが、運転室を出るのはやはりためらわれた。トラクターを運転しながら後ろをふりむくと、暗闇のなかにオオカミたちの目が緑の光を放っていた。

|

|
 |